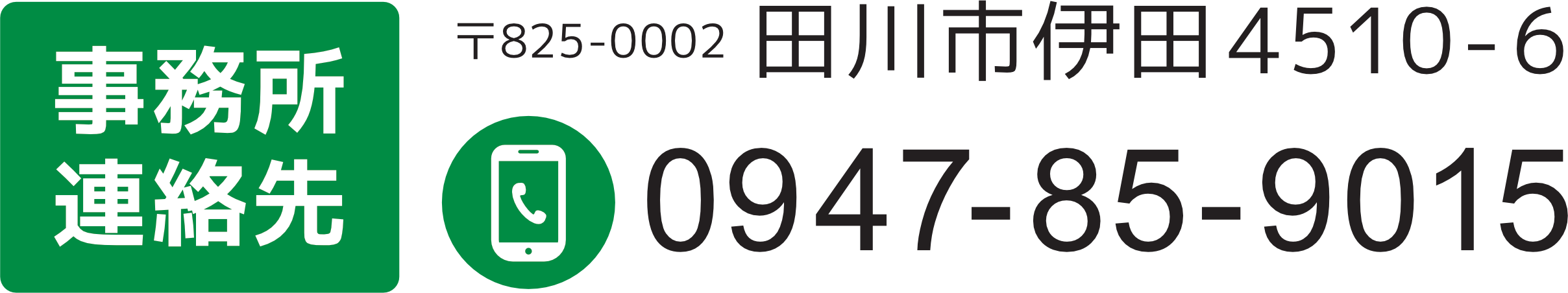本文の始まりです
学校行事は児童生徒と教職員が主役だ
2008年10月18日
今日、朝は
金魚の水替え(写真は金魚の体調を確認しているところ)。その後は山口はるな衆院予定候補の選挙準備や「まこと通信」の作成に追われました。
やっていることはたくさんあるのですが、文章となるとこれぐらいの内容になってしまいます・・・。
話は変わり・・・
とても気になる記事があったのでここで紹介します。以下は引用です。
国旗・国歌なし 埼玉県立盲学校100周年行事 知事や教育長も招待せず
埼玉県立盲学校(川越市)が11月の開校100周年記念行事で、国旗掲揚や国歌斉唱を行わないことが18日、分かった。県教委は「周年行事の形式は校長の判断に任せている」として指導は行わない方針だが、「きちんとやるべき」との声も上がっている。
記念行事は11月2日、文化祭の一部との位置付けで、在校生の合唱や演劇などを行う。知事や教育長は招かないという。
県内にある県立学校は高校と中学、盲学校など特別支援学校の計179校。県教委によると、県立学校の周年行事は、実施の有無や形式などすべてが校長の判断に委ねられている。
県立盲学校では、視覚障害と知的障害が重複した在校生も多いため全員が長時間の式典に参加するのは難しいと判断し、式典の形式をとらなかったという。
ただ、県内でこれまでに開校100周年の節目を迎えた高校計11校は式典を行い、国旗掲揚、国歌斉唱を実施。東京都では特別支援学校を含め、全都立学校の周年行事で国旗掲揚、国歌斉唱が行われている。
竹並万吉県議は「県立学校の責任者である知事や教育長を招かないのも異常」と指摘している。
(引用終了)
国旗国歌の問題も式典まで言い出したら、運動会・文化祭などすべての行事で国旗国歌を斉唱奉り、知事や教育長を呼び一人づつ生徒が貧血で倒れるまで挨拶をさせるのですかね。
私はそれ以上に、ある県議の「県立学校の責任者である知事や教育長を招かないのも異常」という言葉のほうが気になります。
なぜこの県立盲学校が式典形式をやめ、来賓も極力抑えているのか。それは
「視覚障害と知的障害が重複した在校生も多いため全員が長時間の式典に参加するのは難しいと判断」
としているから、ただそれだけです。まさに生徒のために時間を短くしようという学校現場の配慮にほかなりません。
しかし知事や教育長が恭しくきて、とても対応がデリケートな障がいのある生徒を前に延々と祝辞を述べるのが、記念式典のあるべき姿なのですかね??
また学校現場にとって「来賓」の対応はかなり大変です。事実私も来賓として学校現場に訪れることがありますが、来賓には過剰なまでの接待があることもあります。
おそらく現場の教職員は来賓が来たときの対応を事前にいろいろ考えているんだろう、というのがすぐに分かるような動きをするのです。その事前の打ち合わせだけでも、子供と接したり考えたりする時間を削るのですから、それは現場にとってリスクです。
今回の式典も、別に来賓のためにするのではありません。学校現場は児童生徒と教職員が主役の場です。学校で行われる様々な行事は、児童生徒と教職員にとって満足する式典であればよい、と私は思います。